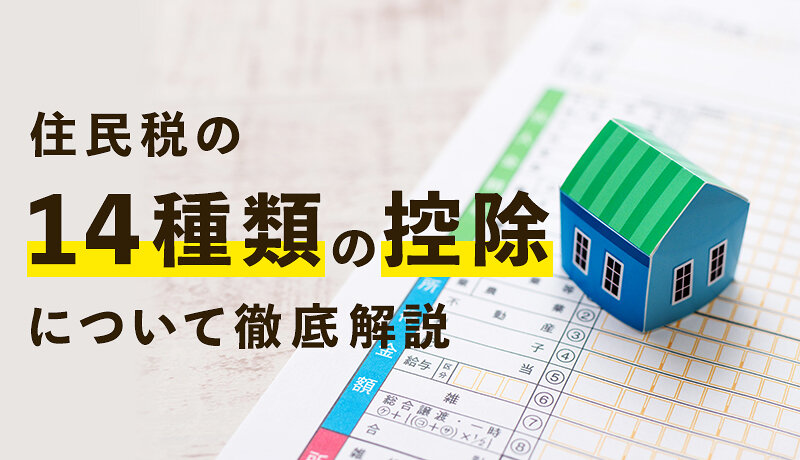
住民税の14種類の控除について徹底解説!申告が必要なものについても紹介
住民税の控除の種類は多く、控除に申告が必要なものもあります。
日本の税金の仕組みは納税額の不足には厳しいですが、払い過ぎてしまった場合は誰も忠告しませんし、申告しなければ返してもらえません。
つまり、控除を知らなければ払い過ぎた税金を取り戻す手段を失うことに直結します。
また、令和2年から適用される住民税の控除の改正点もあるので、これまでの住民税を知っている方でも見直したほうがよいでしょう。
今回の記事では住民税の14種類の控除について詳しく解説します。
住民税の14種類の控除
住民税には14種類の控除があります。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- 寡夫控除
- 勤労学生控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①基礎控除
基礎控除とは、所得税や住民税の計算において、すべての納税者が一定の金額を所得から差し引ける制度です。
この控除によって、税金を支払うための基礎となる所得が減り、結果的に税金の負担が軽くなります。
2020年以降、基礎控除の額は以下のようになっています。
- 所得税の場合:一律で48万円が控除される
- 住民税の場合:一律で43万円が控除される
この基礎控除は、基本的にすべての納税者が利用できます。会社員、個人事業主、年金受給者など、収入がある人全員が対象です。
ただし、所得が2,400万円以上になると控除額が減り、2,500万円以上になると基礎控除を受けることができません。
②配偶者控除
年間所得が48万円以下(令和1年までは38万円)の配偶者を有する納税者に適用される控除です。
ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
納税者の年間所得金額と控除の対象になる配偶者の年齢によって、控除金額が異なります。
70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となり、70歳以下の配偶者は一般控除を受けることになります。
それぞれの控除金額について下記の表にまとめました。
| 合計所得金額 | 一般控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超え950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超え1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
③配偶者特別控除
配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者特別控除は受けられる場合があります。
年間所得が48万円以上133万円以下であれば、配偶者控除に代わって適用されます。
控除額は納税者の所得と配偶者の所得によって異なります。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| - | 900万円以下 |
900万円超え 950万円以下 |
950万円超え 1,000万円以下 |
|
48万円超え 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
|
95万円超え 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
|
100万円超え 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
|
105万円超え 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
|
110万円超え 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
|
115万円超え 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
|
120万円超え 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
|
125万円超え 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
|
130万円超え 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
④扶養控除
年間所得が48万円以下(令和1年までは38万円)の親族を有する納税者に適応されます。
配偶者以外の親族の範囲は6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、養子や養護を委託された老人がいる場合も控除が適応されます。
また、扶養者の年齢によって控除金額が異なり、19歳~23歳未満の場合は63万円です。70歳以上の場合は48万円となり、それ以外の扶養親族は38万円が控除金額になります。
また、同居老親(納税者または配偶者の直系尊属)の場合は控除金額は58万円になります。
⑤障害者控除
納税者が障害者であるか、障害者を配偶者、扶養親族に有する場合に適応される控除です。
控除額は障害の度合いによって異なり、普通障害者であれば27万円、特別障害者であれば40万円です。
⑥寡婦控除
納税者が寡婦である場合に適応される控除です。
一般寡婦の場合は27万円が控除されますが、子を扶養している場合は特定寡婦と認められることがあり、その場合は35万円が控除されます。
⑦寡夫控除
妻と離婚・死別した後婚姻をせず、子を扶養している場合は寡夫控除を受けられます。
控除額は一律して27万円です。
⑧勤労学生控除
学生の年間所得金額が65万円以下で、給与所得以外の収入が10万円以下の場合に適用される控除です。
控除額は一律して27万円です。
⑨雑損控除
納税者が災害、盗難、横領などの損失を被った場合に適用される控除です。
次の2つの項目で多い方の金額が控除されます。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
⑩医療費控除
医療費控除は、納税者本人または配偶者、扶養親族にかかった医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。
医療費控除額は、支払った医療費の合計額から、年間所得の5%または10万円のうち、いずれか少ない方を差し引いた金額が控除対象となります(控除上限は200万円)。
たとえば、年間所得が200万円の場合、5%は10万円なので、10万円を差し引きます。年間所得が100万円の場合、5%は5万円となるため、5万円を差し引いて医療費控除額を算出します。
⑪社会保険料控除
納税者が社会保険料を支払った場合に適用される控除です。
控除額は支払った社会保険料の全額です。
⑫小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済掛金、確定拠出年金に係る企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った場合に適用される控除項目です。
支払った金額すべてが控除されます。
⑬生命保険料控除
住民税における生命保険料控除とは、納税者が生命保険、介護医療保険、個人年金保険に支払った保険料に対して、一定額を所得から控除できる制度です。
この控除を受けることで、住民税の負担を軽減することができます。
また、この制度は、平成24年1月1日以降に契約した保険と、平成23年12月31日以前に契約した保険では適用方法が異なります。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額は、以下を参考にしてください。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
| 32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
控除の対象となる保険料は、原則としてその年に実際に支払った保険料です。
注意点として、新契約と旧契約では控除の適用される額が異なるため、支払った保険料がどの契約に基づくものかを事前に確認しておくことが大切です。
⑭地震保険料控除
地震保険料を支払った納税者に適用される控除です。
年間の支払い保険料の合計が5万円以下の場合は全額、5万円を超えるようであれば一律して5万円が控除されます。
申告が必要な住民税の控除
14種類の住民税の控除の中で、申告をしないと控除が受けられないものは何でしょうか?
医療費控除と雑損控除を受ける場合は申告が必要です。
確定申告をしている人は問題ありませんが、年末調整で税金を確定させている場合は控除を受けるために別途申告する必要があります。
所得税と住民税の基礎控除の違い
所得税は、基礎控除額が一律48万円です。
ただし、納税者の合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に控除額が減り、2,500万円以上では基礎控除が適用されません。
所得税の税率は、累進課税制度が採用されており、所得が高くなるほど税率も上がります。控除後の所得に対して5%から45%の税率が適用されます。
住民税は、基礎控除額が一律43万円です。
所得税と同様に、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が減り、2,500万円以上では控除がなくなります。
住民税の税率は、一律で課税され所得にかかわらず税率は基本的に10%です。
住民税控除のまとめ
住民税の控除の種類について理解していただけたでしょうか?
覚えることがたくさんあるように思うかもしれませんが、自分が受けられる控除だけ確認するようにすれば申告ができるようになります。
特に医療費控除は医療費を支払っているすべての人に適応され申告する必要があるので、必ず確認しておきましょう。

2016年から活動を開始したフリーライター。マネ会では「クレジットカード」「キャッシュレス」を担当。株式投資、投資信託、不動産投資、住宅ローン、カードローンなどの金融全般の記事を幅広く執筆している。ガジェット、ゲームの紹介記事の執筆経験もあり。常日頃からクレジットカードとキャッシュレスの利用を勧めている。趣味はテレビゲームとアクアリウムと投資、最近は楽天スーパーポイントを使った元手0の投資信託への投資を実践中。


